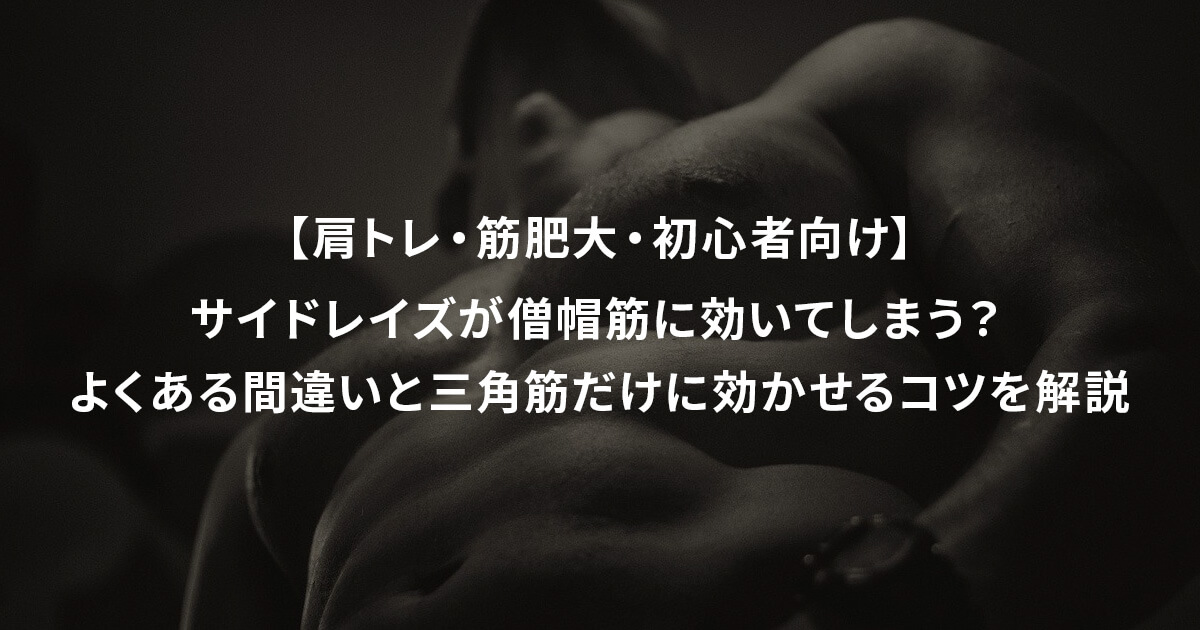筋トレ初心者
筋トレ初心者サイドレイズが僧帽筋に入っちゃうんだよね。
肩の丸みをつくるうえで欠かせないトレーニング種目が「サイドレイズ」。
三角筋中部を狙って鍛える定番種目ですが、実際にやってみると…
- 肩ではなく首や背中(僧帽筋)が疲れる
- 思うように三角筋が張らない
- フォームが正しいのかわからない
そんな悩みを感じたことがある人も多いのではないでしょうか?
「サイドレイズは効かせにくい」「肩より僧帽筋に入ってしまう」と感じる場合、筋力不足ではなくフォームや意識の問題であることがほとんどです。
の記事では、僕自身がサイドレイズを“苦手種目”から“得意種目”に変えた経験をもとに、僧帽筋に効いてしまう原因と三角筋にしっかり効かせるコツを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
 kth6
kth6ショルダープレスが苦手な人はこちらの記事も読んでみてください!
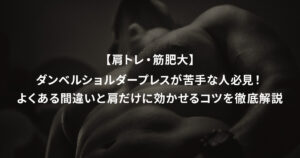
- サイドレイズで僧帽筋に効いてしまう主な原因
- サイドレイズで三角筋中部に効かせるコツ
この記事を書いている人
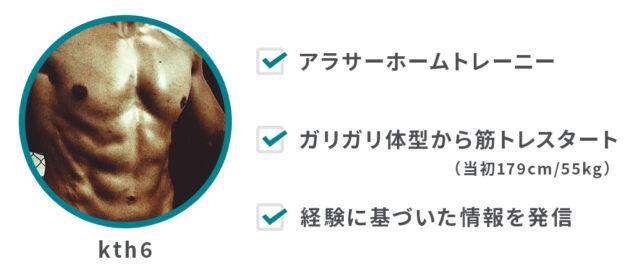
サイドレイズで僧帽筋に効いてしまう主な原因
 筋トレ初心者
筋トレ初心者サイドレイズが僧帽筋に効いてしまうのはなぜ?
サイドレイズをしていて「肩ではなく首や背中(僧帽筋)が疲れる」と感じる場合、その多くはフォームや意識のズレが原因です。
もちろん、正しいフォームで行っていても僧帽筋にまったく負荷が入らないわけではありません。
肩を安定させたり動作を補助したりするうえで、僧帽筋の関与は自然なことです。
ただし、本来サイドレイズでメインで刺激したいのは三角筋中部。
僧帽筋に力が入りすぎて主役が入れ替わってしまうと、狙った部位に十分な負荷をかけられなくなってしまいます。
ここでは、僕自身も以前に陥っていた失敗をもとに、「サイドレイズで僧帽筋に効いてしまう主な原因」を3つに絞って解説します。

動作中に僧帽筋が上下に動いている
サイドレイズで三角筋中部に効かせられない原因の一つが、動作中に僧帽筋が上下に動いてしまうことです。
サイドレイズは三角筋中部を狙う種目ですが、動作中に肩をすくめる癖や腕を上げる際に体の反動を使うと、自然と僧帽筋が上下に動き、補助的に働いてしまいます。
その結果、三角筋中部への負荷が減り、肩の丸みや張りを作る効果も薄れてしまいます。
特に僕自身がそうだったのですが、「肩が疲れない=効いていない」と勘違いして重量を増やしすぎると、肩の力だけでは持ち上げきれず、僧帽筋の上下運動に頼るフォームになりやすいです。
サイドレイズでは肩甲骨を固定し、低重量・高回数でコントロールすることが、三角筋に効かせるポイントです。
 kth6
kth6肩をすくめず、肩甲骨を軽く下げて固定する意識が大切!
動作中に肘が伸びきっている
サイドレイズで僧帽筋に負荷が入りやすくなる原因の一つが、動作中に肘が伸びきってしまうことです。
サイドレイズは肩関節の外転運動で三角筋中部を狙う種目ですが、肘を完全に伸ばすと腕全体が長い棒のようになり肩だけでダンベルをコントロールできなくなります。
その結果、自然と肩がすくみ僧帽筋で補助する形になり、肩に負荷が入りにくい状態となります。
さらに、肘が伸びきった状態では手首に重量がかかりやすく、前腕や手首に不自然な負荷がかかります。
特に重量を増やしたときには、手首のケガや腱への負担が高まるので注意が必要です。
 kth6
kth6肘は軽く曲げたまま、肘でダンベルを上げるイメージ!
反動を使いすぎてフォームが乱れている
サイドレイズで僧帽筋に効いてしまう原因の中でも特に多いのが、反動を使ってダンベルを上げてしまうことです。
本来、サイドレイズは三角筋中部の動きでダンベルをコントロールする孤立種目ですが、勢いをつけて上げようとすると、体幹や僧帽筋の力で動作を補ってしまいます。
特に立ち姿勢で行う場合、膝や腰を軽く使って反動が加わることで動作が「肩の外転」ではなく「全身のスイング運動」に近くなり、三角筋への負荷が大きく減少します。
さらに、反動で勢いよく持ち上げたダンベルは下ろすときにも重力に任せて落としやすくなり、筋肉が最も発達する下ろす動作(エキセントリック局面)をおろそかにしがちです。
サイドレイズの最中は常に負荷を抜かず、いかに小さな動作で狙った部位を動かせるかを意識してみてください。
 kth6
kth6常に肩の外側が張る感覚を意識して、ゆっくり丁寧に!
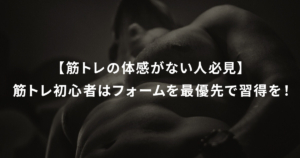
サイドレイズで三角筋中部に効かせるコツ
 筋トレ初心者
筋トレ初心者どうすれば肩に効かせられるようになるの?
サイドレイズで三角筋中部を狙ううえで重要なのは、「姿勢の安定」「動作の軌道」「テンポのコントロール」「重量設定」の4つ。
このどれか一つでも崩れると、動作を僧帽筋や体幹の力で補ってしまい、三角筋中部に十分な刺激を与えられなくなります。
ここからは、僕自身もフォームを見直して実感した三角筋中部にしっかり効かせるための具体的なコツを4つ紹介します。

肩甲骨を下げて固定する
サイドレイズで三角筋中部にしっかり効かせるためには、まず肩甲骨を下げて固定する(下制する)意識が欠かせません。
動作中に肩がすくむと肩甲骨が上方に動き、僧帽筋上部が主導の動きになってしまいます。
その結果、せっかくの刺激が分散され三角筋中部への負荷が減ってしまいます。
これを防ぐため、動作に入る前に軽く胸を張り、肩甲骨を下げてやや内側に寄せる姿勢を作っておきましょう。
この姿勢を取ることで、肩関節の可動域が安定し、三角筋中部が主導して腕を外に持ち上げる動作(外転)がスムーズに発揮されます。
また、立った状態だと肩甲骨が動きやすい場合は、椅子やベンチに座った状態でのサイドレイズを試してみてください。
座って体重を預けることで体幹を安定させられるため、上半身のブレが減り、三角筋中部により集中して負荷をかけやすくなります。
 kth6
kth6座った状態で肩への負荷の入り方を覚えよう!
肘でダンベルを挙げるイメージを持つ
サイドレイズでは、ダンベルを手で持ち上げる意識ではなく、肘で持ち上げる意識を持つことが非常に重要です。
手で上げようとすると腕全体を使う動きになってしまい、肩ではなく前腕や僧帽筋上部が余計に働いてしまいます。
一方で、肘を外に押し出すように動かすことで、肩の外転動作(=腕を横に広げる動き)が自然に引き出され、三角筋中部にダイレクトに刺激を届けられます。
また、肘を軽く曲げたまま、前腕を体のラインより10〜15°ほど前方に出すことで、肩関節が内旋しすぎるのを防ぎ、関節へのストレスを軽減できます。
さらに、ダンベルを挙げる際に小指側を高く上げないように注意しましょう。
一見すると三角筋中部に効いているように感じますが、肩が内旋して肩関節に負担がかかりやすいため、このフォームが原因で痛みを招くケースもあります。
 kth6
kth6よく見るフォームですが…特に肩の柔軟性が低い人や肩に違和感を感じやすい人は要注意!
理想は手首と肘がほぼ水平(または手首がわずかに下)で、前から見たときにダンベルが肘より外側に出ない位置です。
このフォームを保つことで、肘主導の動きが安定し、三角筋中部に一直線で負荷を伝えられます。
肩の高さで止めて、下ろす時もゆっくりコントロール
サイドレイズでは、ダンベルを肩の高さまで上げて止めることが鉄則です。
肩の高さで一瞬静止することで、三角筋中部にしっかりテンションを乗せたまま動作を切り返せます。
 kth6
kth6テンションを抜かない意識こそ、サイドレイズで効かせる大きなポイント!
さらに、下ろす動作(エキセントリック局面)も筋肥大を狙う上で非常に重要です。
重力に任せてストンと落とすのではなく、2〜3秒かけてゆっくり下ろしましょう。
このゆっくり戻す動作によって筋線維がしっかり伸ばされ、筋損傷と回復のサイクルが促進されます。
その結果、軽めの重量でも三角筋中部に鋭く効かせることが可能になります。
 kth6
kth6反動を使わず、上げる時も下げる時もゆっくり負荷を感じながら動作!
低重量・高回数で追い込む
サイドレイズは、重い重量で無理に上げる種目ではありません。
三角筋中部は比較的小さな筋肉群で構成されており、重すぎる重量を扱うとフォームが崩れやすく肩ではなく僧帽筋や体幹の力でダンベルを持ち上げてしまいがちです。
そのため、正しいフォームを保ちながら15〜20回程度できる軽めの重量で限界まで追い込むことをおすすめします。
軽い重量でも筋肉を意識して丁寧に動作することで、三角筋中部の筋線維をしっかり追い込むことができます。
特に最後の数回は、肩に「焼けつくような刺激」を感じるはずです。
この感覚こそが、効かせるサイドレイズの証拠です。
 kth6
kth6セット数は決めず限界まで続けよう!
まとめ「肩から負荷を抜かないフォームを身につけて確実に効かせよう」
筋肥大を狙うなら高重量を扱える種目が基本という認識で、肩トレでもダンベルショルダープレスやミリタリープレスといったプレス系を優先していました。
重量を上げる実感も得やすく、三角筋全体に効かせやすいので効率が良いと思っていたんです。
ただ、三角筋は前部・中部・後部に分かれていて、プレス系だけだと中部のボリュームが十分に出ないことに気づき、レイズ系種目も避けて通れないんだと実感しました。
最初はサイドレイズも他の種目と同じように重量を上げようと頑張っていましたが、フォームが崩れて僧帽筋や体幹に頼ってしまい、肝心の三角筋中部には思うように効きませんでした。
そこで軽めの重量で回数をこなすように改めたところ、地味な作業ながらも三角筋中部に「焼けつくような疲労」が溜まる感覚が分かるようになり、フォームのコツをつかむことができました。
サイドレイズでは、重量よりも回数を重視してひたすら追い込むことで、三角筋中部に効かせることができます。
肩幅を大きく見せたい・逆三角形のシルエットを目指すなら、ぜひプレス系と組み合わせて優先的にやり込んでみてください!